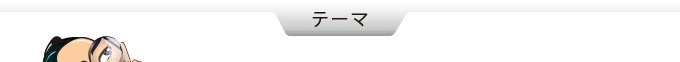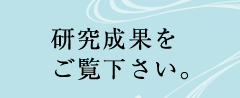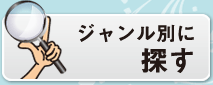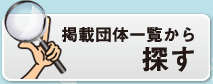荒木町における銭太鼓の歴史と伝承法の研究
荒木町銭太鼓研究会
![]()

昭和の初め、旅芸人から教えられたと伝えられている「銭太鼓」のルーツを探る。町内の盆踊り、酒生地区の文化祭、明日村との交流など、数少ない出演であるが、草創期の婦人や年層別で座談会を開き、意気込みや苦労話を聞きながら「銭太鼓」伝承の道筋も探る。
聞き取りによる情報収集
家庭訪問聞き取りと座談会形式の思い出話を語り合いながら旅芸人より直接習った長老の話を聞く。
銭太鼓について、平成21年福井新聞社の取材を機会や、今までの経過や体験談などを話し合ってもらい地区に伝わる芸能を伝承していく意義を再確認し合った。また、過去の出演者に対しても座談会に参加してもらうように呼びかけた。
資料収集、まとめ
○資料の収集
(1)今までの記録写真の収集(約50枚)
・練習風景
・敬老会出演風景
・生き生き文化祭
・酒生地区外出演
・荒木体育会での様子 など
(2)新聞記事等
・福井新聞
・くみあいだより
・酒生青年会機関誌
・ビデオ(遺跡祭り)
○総括とまとめ
検討会の実施、冊子の作成、情報収集と編集と校正、
パワーポイント資料作成、資料や記録をデータで保存



平成23年度「福井学」推進協力団体の指定を受け、荒木町内のかつての出演者各層に呼びかけて研究を進めるために話を聞いたり写真その他の資料収集始めた。残念ながら戦前の資料は勿論戦後の資料すら収集に残っているのが少なくなっていた。
今回の研究で伝承芸能を守っていくことは社会生活の潤滑油として必要であることへの認識を深めることが出来た。しかし、これを伝えていくことには、伝承芸能に対する意識の高揚は勿論男性の協力、参加を始め子供会に話しかけ、リーダーの育成、出演の機会、経費の問題等難問が山積していることも事実である。