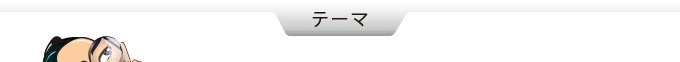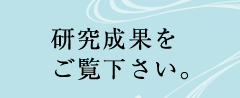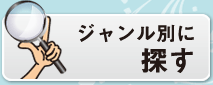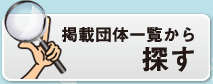隠れた福井の歴史を探る
福井市ボランティアグループ「語り部」
![]()
![]()
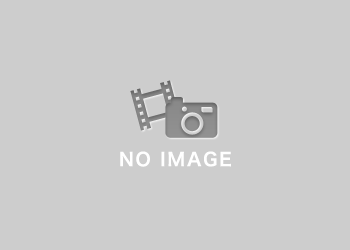
隠れた福井の歴史に目を向け、謎とされている事跡を探索し、調査研究を行い、成果を冊子としてまとめる。各部会に分かれて、調査・取材等を行った。
第1分科会
刀鍛冶「長曽祢虎徹」について
刀鍛冶長曽祢虎徹が、福井に居住していたことはあまり知られていないが、一族とともに来福、息女が正玄家(橘曙覧の実家)に嫁いだことや、虎徹が使用した井戸など、福井での虎徹を探索した。福井市足羽地区にある妙観寺へ視察に訪ねたが、墓が確認できなかったので、刀剣書を元に「江戸時代に全国にその名を響かせた刀工 長曽祢虎徹の墓と妙観寺について調査を開始することになった。福井での居住区や墓や彦根・東京の居住地などを調べ刀鍛冶に必須の井戸を調べた。
第2分科会
「竹林唯七」について
忠臣蔵の赤穂浪士四十七士の一人武林唯七の墓が福井にあったと、写真家故八木源二郎氏が執筆した「カメラ風土記」にある。八木氏が果たせなかった由来の探索を語り部が引き継いだ。唯七の墓があったとされる法興寺墓地内を現地調査したり、唯七が使ったとされる刀について、専門家から聞き取り調査を行ったりした。忠臣蔵を今一度調べ、越前武生藩やその家臣たちが討ち入りに深く関わっていたことを調べた。
第3分科会
福井藩士殉死七士について
三代藩主松平忠昌公が死去した当時、ご法度だった殉死をした福井藩士七士。その心意気に対しての松平家の対応、墓碑の存在、遺族や願い、寺の今日について探索した。永平寺・松平公廟所・七士ゆかりの寺を訪ね歩き調べていった。
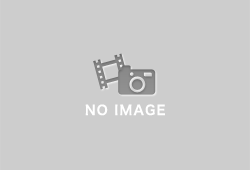
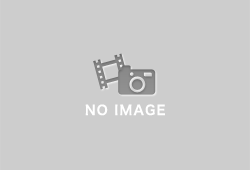
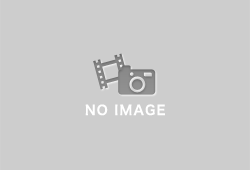
各部会での調査・研究をまとめたものを「埋もれた福井の宝」と題して冊子を発行し、公的施設(公民館、図書館、学校等)・助成団体に配布した。